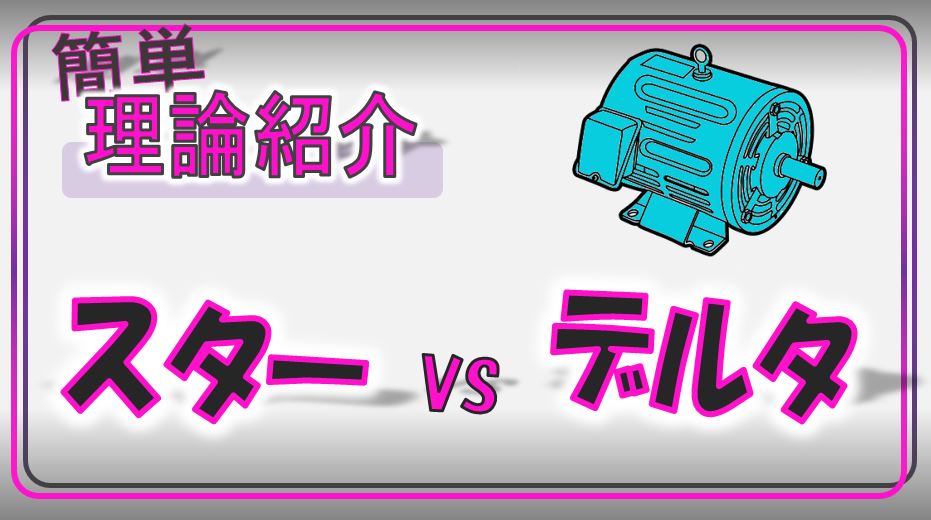何故スター結線のモータは、デルタ結線より電流値を低く抑えられるのか
モータに関するスター結線とデルタ結線の理論の紹介
どの電流を比較するのか
![]()
前回の授業で、 モータにおけるスター結線とデルタ結線の違いに関して学びました。スター結線はデルタ結線と比較して電流値を低く抑えることができます。
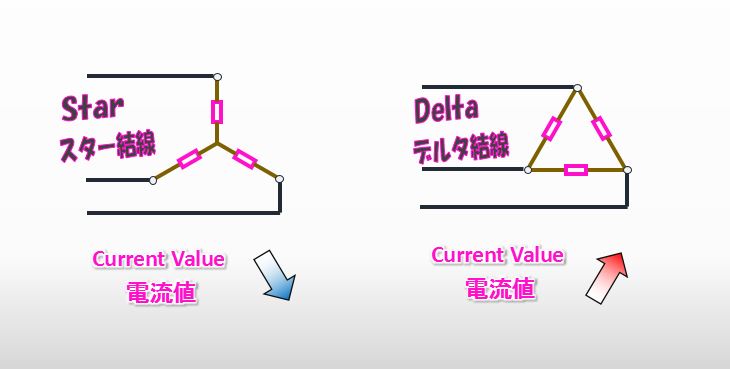
![]()
そうだね。
![]()
でも そういった違いが生じる理由がまだわからないです。何でスター結線ではデルタ結線より電流値が小さくなるのでしょうか?
![]()
まずは、何で 三角関数の計算を複素数で置き換え…
![]()
小難しい数学の話は無しでお願いします!
![]()
そうか。。数学の話は なるべくしないようにするよ。。
![]()
どうも。
![]()
ところで、どの電流の大きさをスター結線とデルタ結線で比較しているの?
![]()
はい?
![]()
スター結線の電流はデルタ結線の電流より小さくなる ってことを学んだんだよね?
![]()
そうですけど?
![]()
どの電流を比較してるの?下の図の電流値?
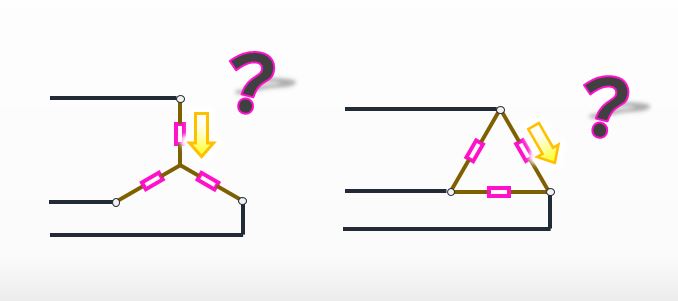
![]()
えぇっと。。わかりません。。
![]()
実は、以下の図の電流値を比較しているんだ。
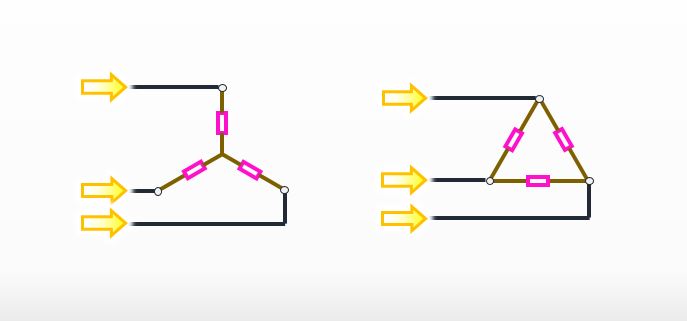
![]()
その電流は、他の電流より重要なんですか?
![]()
そういうわけではないけど、その電流を比較するってことは、モータに流れている電流の大きさを比較するのと同じことになるんだ。
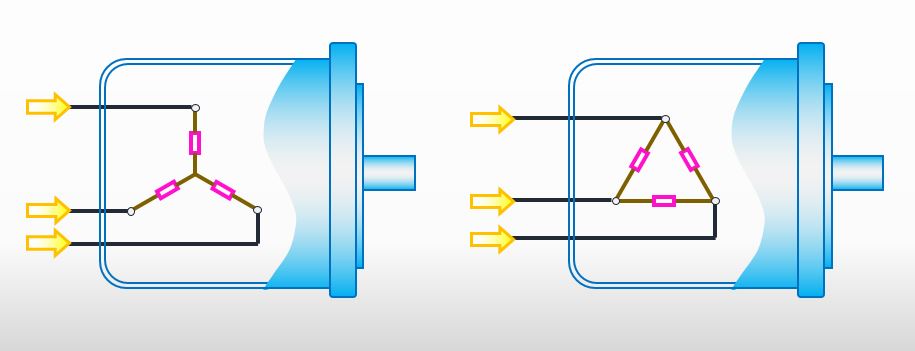
![]()
モータに流れている電流値を知ることは有効かもしれないですね。
![]()
そうだね。もしもモータに大量の電流が流れているのなら、モータがかなり頑張ってる ってことがわかるしね。
![]()
ちなみに どうやってモータに流れている電流値を測定するんですか?
![]()
クランプメータってのは 聞いたことある?
![]()
ありますけど、実際に使ったことはないです。
![]()
下の図を見れば、クランプメータの使い方は一目瞭然かな?
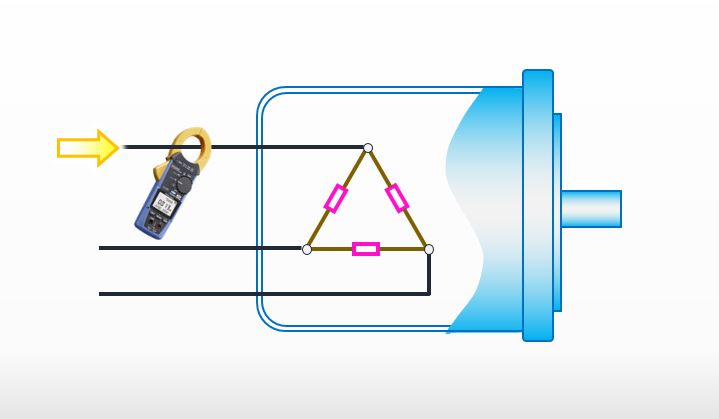
![]()
そうですね。実際に使っている様子を想像できました。
スター結線における電流値を求める
![]()
じゃぁ 本日のメインテーマに移ろうか。
![]()
メインテーマって 何でしたっけ?
![]()
マジ? スター結線の電流が小さくなる理由を知りたかったんじゃないの?
![]()
よくご存じで。
![]()
まぁ。。。じゃぁ、まずは 以下の図に示された電流値を求めよう。その後で、それぞれの電流値を比較してみよう。スター結線の電流値の方が小さくなるはずだよ。
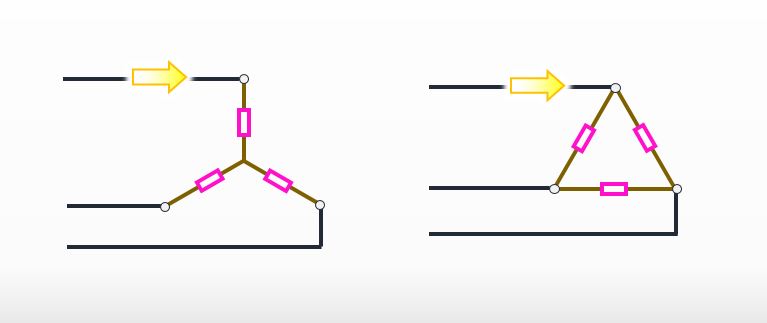
![]()
興味深いですね。
![]()
まず質問なんだけど、下の図の V は何ボルトだと思う?
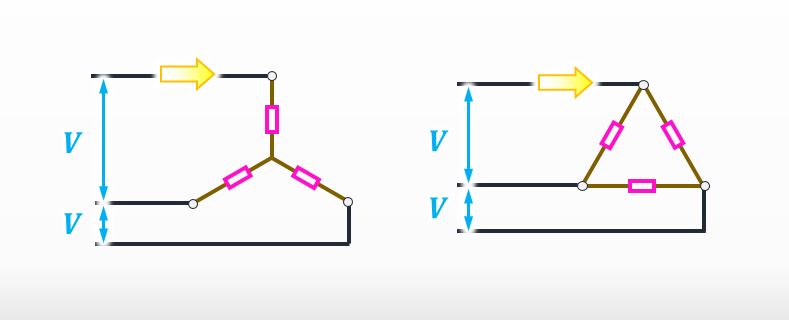
![]()
それは工場によりますね。国によっても異なり、400ボルト程度だったり200ボルト程度だったりします。
![]()
よく知ってるじゃん。じゃぁ別の質問させてもらうね。以下の図において電流値 Iy の値を求めるためには、どんな情報が必要かな? Z を*抵抗値として使用していいからさ。
*正しくはインピーダンスです。
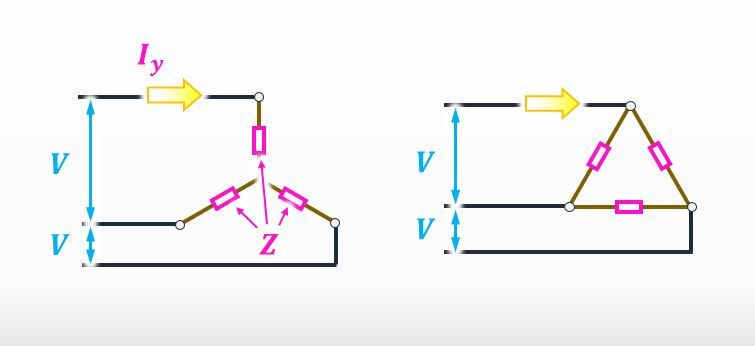
![]()
Iy を求めるためには、以下の図のVy の値を知る必要があります。
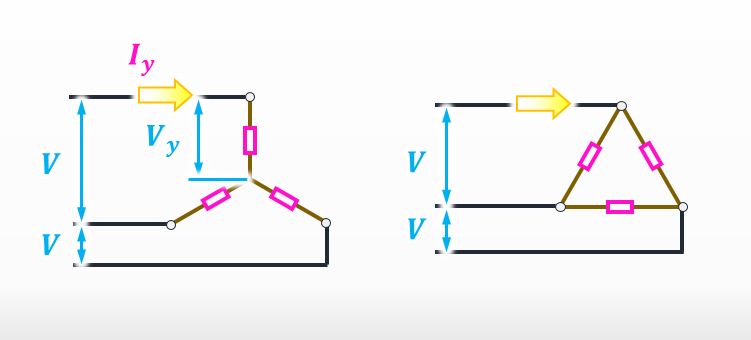
![]()
何でそう思うの?
![]()
もしも Vy の値がわかれば、下の図の赤い枠内でオームの法則を使うことができるからです。
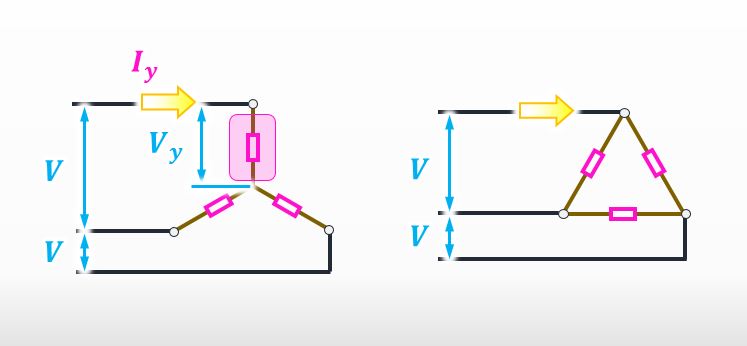
![]()
そのオームの法則ってやつを見せてくれる?
![]()
これです。
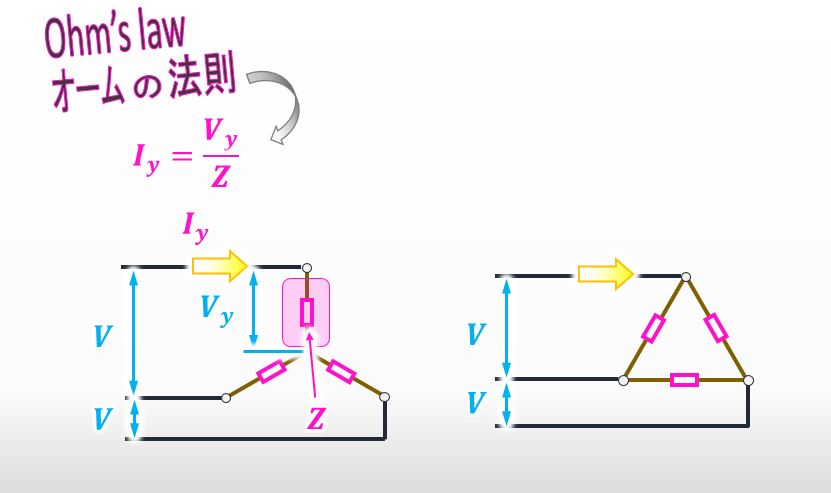
![]()
ワォ.. いきなり天才になったね。じゃぁ いま私たちが知らなきゃならない唯一の値は
![]()
Vy です!
![]()
そうだね。で、Vy の値をどうやって求めればいい?
![]()
簡単ですよ。下の図の黄色い回路に着目して下さい。回路中に2つの抵抗があって、しかもその抵抗値は同じ Z なんですよね?
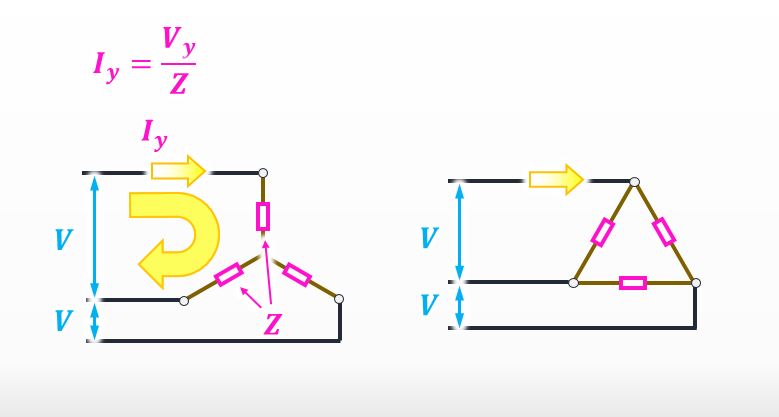
![]()
とうことで、電圧Vは、その2つの抵抗に等しく分散されます。電圧Vyは V/2 となります。
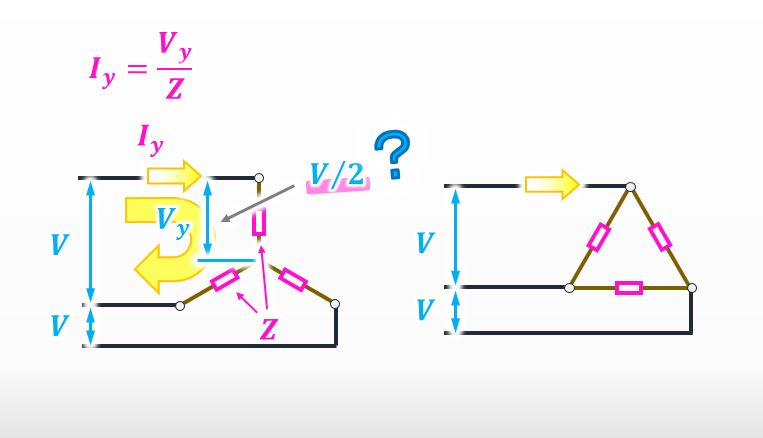
![]()
そうなの?
![]()
間違ってます?
![]()
実は、そんなに単純じゃないんだ。もしこれがDC回路だったら君の考えで合っているんだけど、今回は三相交流じゃん。Vy を求めるためには別の方法を取らなきゃならないのよ。
実を言うと、 Vy は V の半分ではなく、下図の様に ルート3で割った値になるのよ。
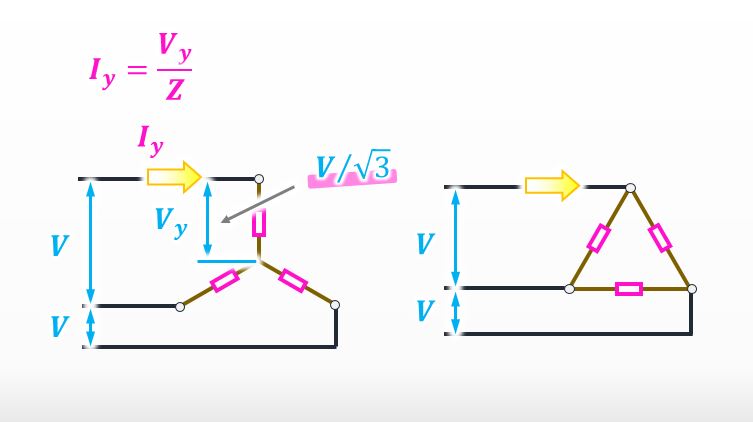
![]()
何でですか!?
![]()
もし理由を知りたければ、この授業が参考になるかもよ。
![]()
後で見てみます。
![]()
どうも。じゃぁ授業に戻ろう。
Vy の値がわかったから、Iy の値はすぐに求まるよね。オームの法則を使って出来た式に、ただ代入するだけだから。
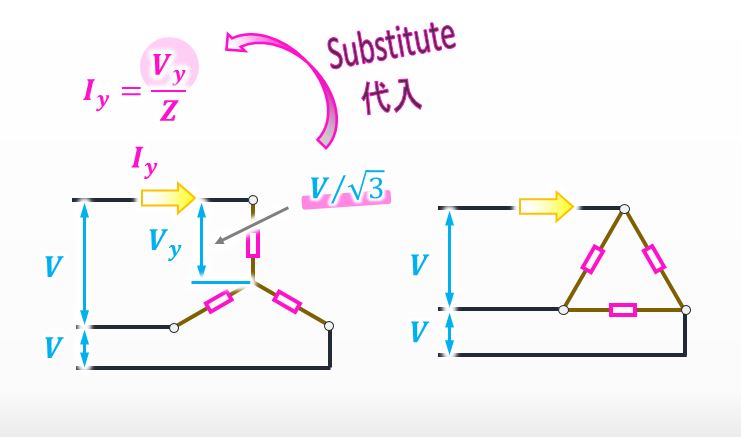
![]()
はい。Iy を求めることができました。
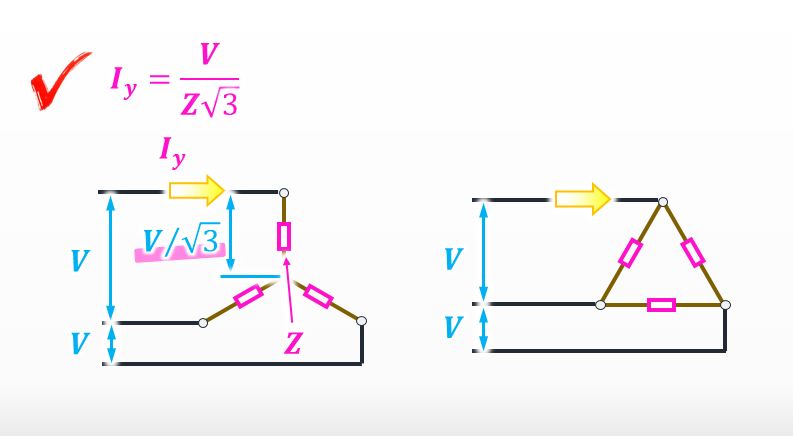
デルタ結線における電流値を求める
![]()
次はデルタ結線の電流値を知りたいですよね。下図示した様に、デルタ結線の電流を Iδ としました。スターデルタの理論によると、Iy は Iδ よりも小さくなるんですよね?
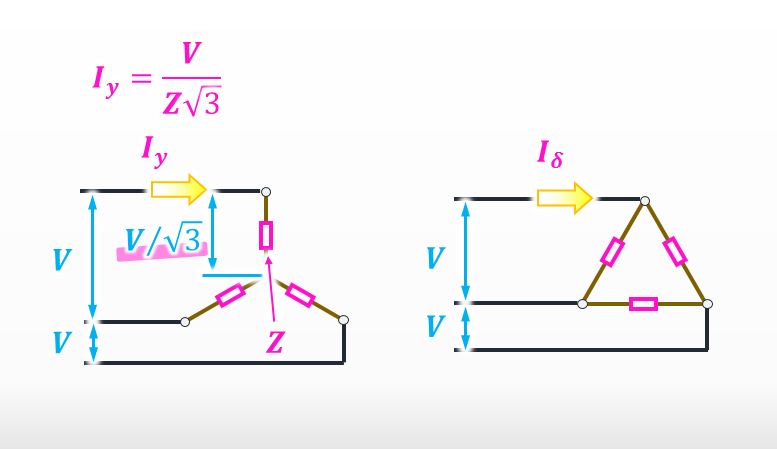
![]()
そうだね。一緒に確かめてみよう。で、どうやって Iδ を求める?
![]()
そうですね… まず、Iδは以下の図の様に2つに分かれるので、*抵抗を通る電流はそれぞれ Iδ/2 となります。
*正しくはインピーダンスです。
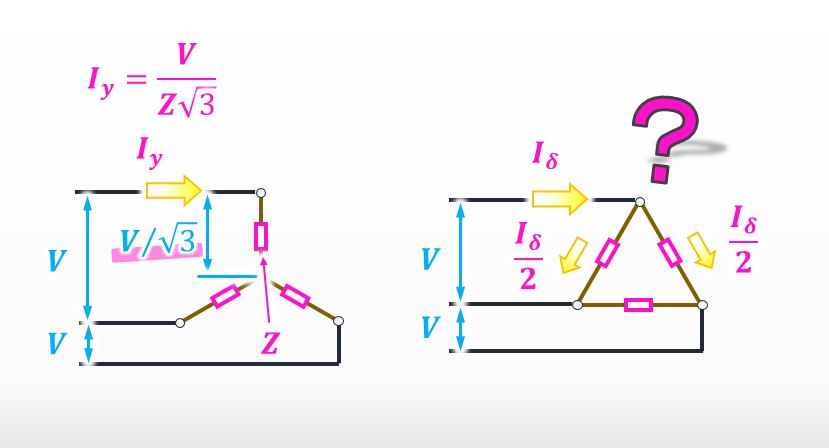
![]()
で、下図の赤い枠内にオームの法則を使ってみました。これでもう Iδ は求まったと言えますね。

![]()
その考えは、直流回路でしか成立しないんだよね。。
![]()
またですか!?
![]()
Iδ は以下の図の様に2つの電流に等分される って言ってたけど、交流回路ではそうはならないのよ。
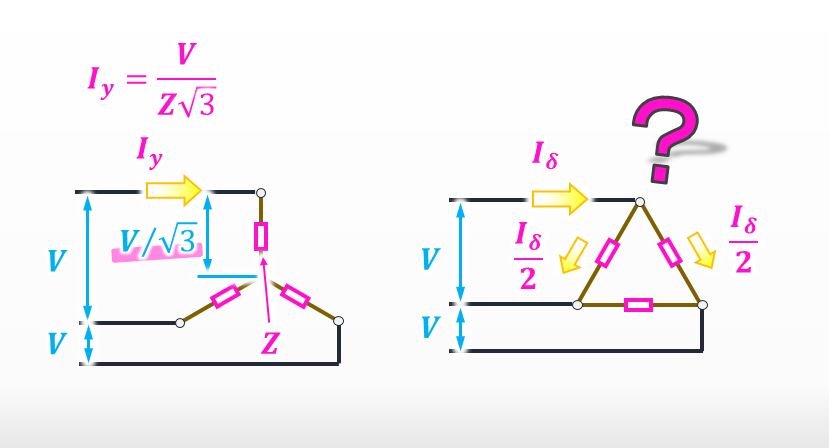
![]()
もし Iδ が等分されないのだとしたら、どうやってIδは2つの抵抗に分配されるんですか?
![]()
Iδ は半分に分かれるのではなく、下図の様に Iδ をルート3で割った値になるのよ。
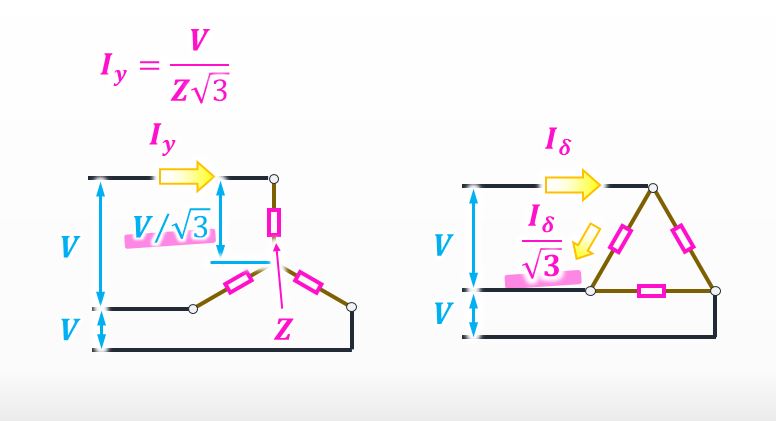
![]()
そうですか。。なんだかIδの分配のされ方って、スター結線におけるVの分配のされ方と似てますね。
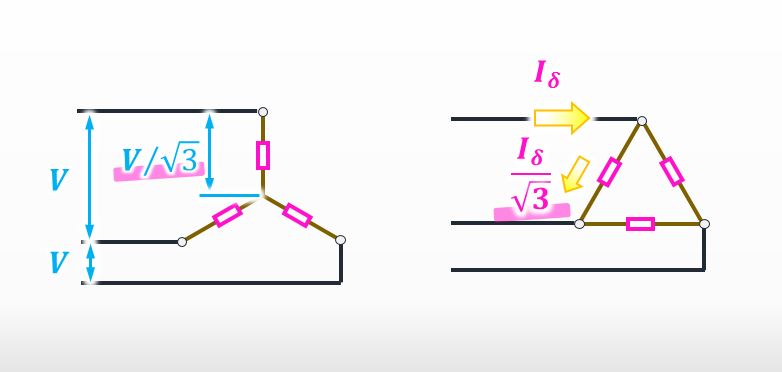
![]()
そうだね。機会があったら理由を説明するよ。三角関数と複素数の関係 がわかっていれば、難しい話じゃないからさ。
じゃぁ授業に戻ろうか。Iδ を求めることは出来る?実はもう Iδ を求める材料は全てそろっているんだけど。
![]()
できます。下図の赤い枠内にオームの法則を使いまして、下の式を求めることが出来ました。
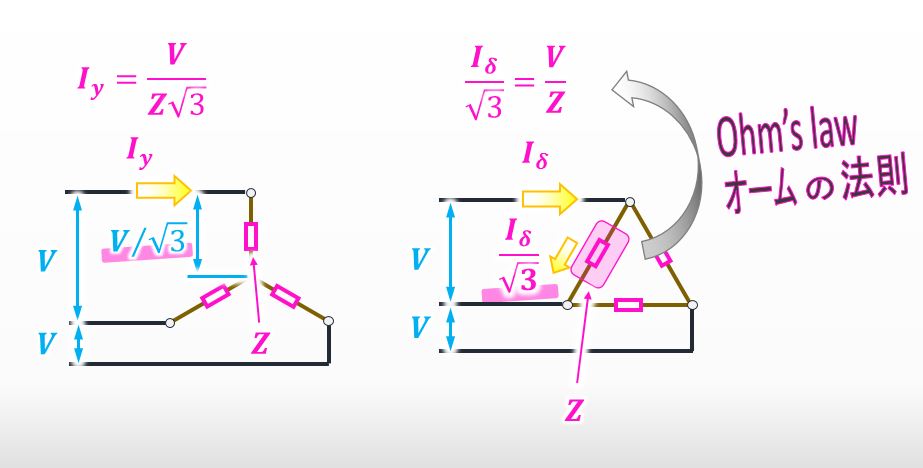
![]()
いいね。じゃぁその式を Iδ について解いてもらえる?
![]()
もちろん。両辺にルート3を掛けるだけです。はいどうぞ。
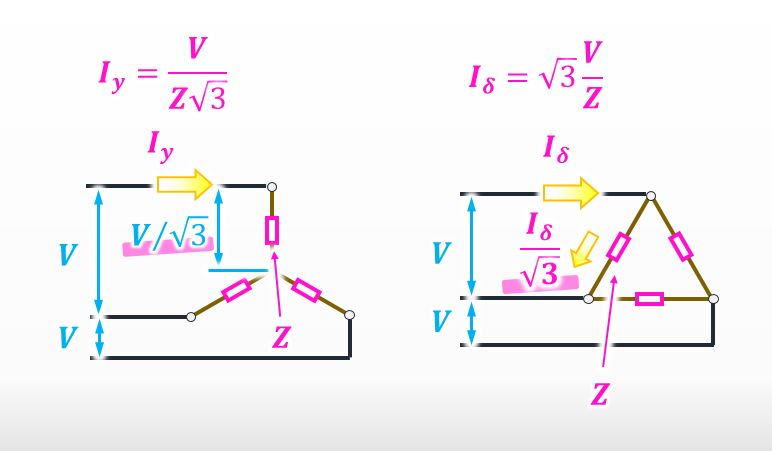
スターとデルタで電流を比較する
![]()
どうも。これでスター結線の電流とデルタ結線の電流が求まったね。ってことで、この授業も最終段階に入ったわけよ。
![]()
Iy と Iδ を比較するってことですね。
![]()
だね。下の図を見てごらん。スター結線の電流値はデルタ結線の1/3になっていることが わかるよね。
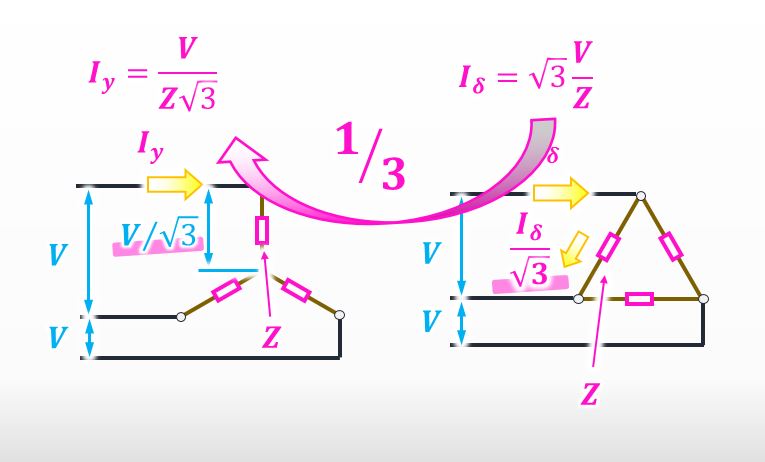
![]()
ホントだ。
![]()
ってことで、スター結線は電流を低く抑えられるってことが証明されたわけだ。
![]()
どうもありがとうございました。